![]()
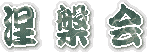
| 2月15日は、お釈迦さまがクシナガラでお亡くなりになった日にあたります。 お釈迦さまはお亡くなりになって、究極的なさとりの境地、涅槃(ねはん)に入られました。 それで、ご本山では2月15日に「涅槃会(ねはんえ)」とよばれる法会が勤められます。 |
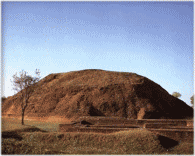
クシナガラ
この涅槃にまつわる昔話はたくさんあります。
そのなかのいくつかを紹介しましょう。
ねこが涅槃図にえがかれないわけ ねこが十二支(えと)にいないわけ 十二支のはじまり へびとかえる すずめとつばめ
| ねこが涅槃図にえがかれないわけ |
| お釈迦さまがおなくなりになったとき、すべての生き物がお釈迦さまのそばに集まって泣いたんだそうです。 でも、その中のネコだけが笑っていました。それで、お釈迦さまの涅槃の絵にはネコの姿がえがかれなくなってしまったんです。 |
この絵にはネコが描かれてます。
| ねこが十二支にいないわけ |
| むかし、むかし、お釈迦さまが病気になられました。そこでけものたちが集まって、なんとかしてお助けしたいと、いろんな相談をしておりました。 そんなとき、お釈迦さまのおうちの前の大きな大きな甘茶の木に、神さまが投げてよこした薬がひっかかってしまいました。けものたちは、 「おまえ、登ってとってこい。」 「おまえこそ登れよ。」 といいあっていると、からだの小さいネズミがとび出して、甘茶の木にするするっと登っていきました。そして、木の先にたどりついて薬を取ろうとしたら、木のかげからネコがとび出して、あっというまにネズミを食べてしまいました。それでお釈迦さまは薬をのみそこね、とうとう亡くなってしまいました。 それでネコは、このときから十二支をはずされてしまったんだそうです。 |
| 十二支のはじまり |
| むかし、むかし、お釈迦さまの具合が悪くなって、国じゅうのけものたちが見まいにかけつけました。 たくさんのけものたちが、われ先にといっしょうけんめい走っていきます。からだの小さいネズミも走りましたが、からだが小さいものだから、大きなものにふみつぶされそうになってしまいます。 そこで考えたネズミは、行列のいちばん先を走っているウシにとびつきました。ウシのしっぽをしっかりとつかまえて、ウシがお釈迦さまの家の前につくと、ネズミはウシのあたまの上からひょいっととびおりて、ウシより先に家の中へ走りこんで一番乗りしたんだそうです。  お釈迦さまは、来たもの順に十二支を決められたそうです。それで、子(ネ)・丑(ウシ)・寅(トラ)・卯(ウ)・・・と、ネズミがいちばん先に置かれて、いばってるんだそうです。 |
| へびとかえる |
| むかし、むかし、天竺の国で、お釈迦さまがおなくなりになるといううわさが、国じゅうにひろまりました。 そこで国じゅうの人が悲しみ、菩薩や尊者、たくさんの人たちがお釈迦さまのところにかけよりました。 動物たちも気が気でなく、自分たちの寿命や食べ物を、お釈迦さまにおたずねしようと集まりました。 ところが、ヘビはうっかりと昼寝してしまって、行くのがおくれてしまいました。あわててかけつけると、お釈迦さまのところから帰ってくるカエルに出会いました。ヘビは、 「しまった。おそかったか。」と思って、カエルに、 「これからかけつけても、間にあわないかなぁ。」 と聞くと、いつもヘビのことがきらいだったカエルは、 「もう手おくれよ。お釈迦さまの臨終に間にあわないようなやつは、観音さまにも見放されたやつだ。これからは土の中にすっこんで、いばらんほうがいい!」 といいました。ヘビは、 「おくれたんだから、それもしかたがない。でも、何か食べなきゃ生きてはいけない・・・。」  というと、カエルはいい気になって、 「おまえなんか、観音のけつでも食らえ。」 っていって、やぶの中へとにげこみました。 その後、ヘビは土の中に住むようになり、カエルは「観音のけつでも食らえ」といったばかりに、ヘビに尻のほうから食われるようになったんだそうです。 |
| すずめとつばめ |
| むかし、お釈迦さまがなくなられるとき、鳥たちに、 「みんな、集まってこーい。」 と知らせたそうです。 いちばん真っ先にとんできたのは、スズメでした。 スズメは、ちょうどおはぐろをつけてたところに知らせがきたものだから、半分つけたまんまで急いでとんでいきました。 ツバメもちょうどおはぐろをつけてたところに知らせがきたんだけれど、「おはぐろをつけてから」っといって、ゆっくりとおはぐろをつけてたんだそうです。その上、紅までつけて。だから、ツバメはいちばん最後になったんだそうです。 それでお釈迦さまは、 「スズメは、感心もの。今日からは五穀を食べなさい。」 「ツバメは、こんなときでもゆっくり化粧しておくれて来たんだ。そのバツとして、今日からは虫けらだけを食べなさい。」 と、決めたんだそうです。  それで、スズメは今でもくちばしの半分が黒く、五穀を食べ、ツバメは紅をつけてお洒落してるから、虫けらだけを食べて過ごしてるんだそうです。 |
![]()
【参考】
『日本の仏教民話集』
稲田浩二監修・前田久子・山根尚子編著
東方出版
2000/02/15