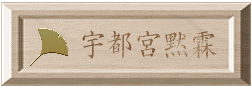
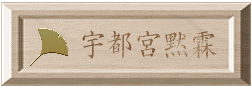

| 宇都宮黙霖は、明治維新の勤皇僧として、吉田松陰・月照たちと交わって討幕に奔走し、数奇な運命のもとに活躍した人物であります。 |
|
幼名は宇都宮采女といい、法名を覚了、または黙霖といいます。 文政7年(1824)に長浜で生まれましたが、その一生は誠に不遇な出生から始まっております。 |
|
3歳の秋、八本松阿弥陀堂の堂守一道のもとに養子に出されました。 一道といっしょに農作業に従事していましたが、なかなかいうことを聞かず、7、8歳の頃に手習修行のためとして長浜へと帰され、しばらく母のもとで暖かい養育を受けることになりました。 後に一道のもとへ連れ戻されますが、どうしてもその生活になじめず、ついに母のもとへと逃げ帰り、一道に義絶され、長浜での生活が続くこととなります。しかし、不倫の子、日陰者といじめられながらの日々は、あまりにもつらかったのでしょう。手のつけようのない腕白小僧に育ってゆきました。 |
| 叔父にあたる専徳寺の常諦は、この腕白小僧をわが子のようにかわいがっていましたが、その腕白ぶりを見かねて、『大学』の素読を授け、勉学の道を勧めました。 時に15歳。この頃から心機一転、学問に志すこととなったのです。 |
| その後、西条町の漢学者野坂由節に師事し、次いで蒲刈島弘願寺円識(石泉和上の弟子・本願寺派勧学)について宗学を学び、さらに円識の奨めで、天下に師を求めて遊学し、広島の坂井虎山(芸州きっての儒学者)・木原桑宅・肥前平戸の光明寺拙厳勧学などを尋ねていったと伝えられています。 |
|
そんな黙霖でしたが、20歳の頃、大阪で大病を患い、長浜に帰って療養しました。しかし、その結果耳が聞こえなくなり、その後はすべて筆談を用いることになりました。 弘化2年、22歳の夏に得度して本願寺の僧籍に入り、法名覚了となります。 |
|
嘉永5年、江戸に上って老中阿部伊勢之守正弘に、尊王抑覇の論稿を送って、反幕府的思想を確立し、ひとり勤皇討幕論を叫んで人身を驚かせました。 そのため、安政元年、幕府・広島藩からの追及を受け、父峻嶺にも厳しい詮議が及びましたが、よく逃れて、また流浪の旅を続けます。 |
|
安政2年、萩に赴き、吉田松陰の『幽囚録』を読んで感動し、獄中の松陰に書を送って文通を繰り返して、松陰に大きな思想的影響を与えたといわれております。 松陰が「時局観を先にし、攘夷の為に尊王論を統一し、人身を一に帰せしむべし」と考えたのに対し、黙霖は「国体論を第一にし、攘夷の有無に拘らず尊王を叫ぶべきである」と主張しました。また、松陰が幕府に対して、その誤りを諌める考えであったのに対し、黙霖は徹底的に討幕を主張して、松陰に思想的転換を与えたのです。 |
| 安政の大獄の際に、頼三樹三郎・梅田雲浜などといっしょに捕らわれましたが、僧形のために釈放されたとか、広島藩に捕えられ、棺に入って脱出し、山口に逃れて毛利家の歓待を受けたともいわれています。 再び広島藩から幕府に渡され、大阪にいた時、ようやく明治維新を迎えることとなりました。 |
|
明治2年に釈放され、還俗してからは宇都宮真名介と名乗りました。 |
明治10年頃、長浜へと帰り、石泉文庫にある大蔵経を読破して、この和訳を行い、それから約20年間を費やして46万首の和歌の形式に整えております。
その中の35万首が現在石泉文庫に遺されています。
若い頃から詩や和歌を好み、20歳の頃につくった『菊花の詩』は、志士の間で愛好されたといわれております。
| 明治14年頃から呉市の沢原家(当時の郡長で、従来から交友があった人)の食客となり、安芸郡役場の嘱託として晩年を送り、明治30年に74歳でその一生を終えました。 当時の総理大臣伊藤博文が広島へ来られた時、一度黙霖先生にお会いしたいとわざわざ呉まで尋ねて来て、「先生」「先生」と呼ぶので、周りの人は一様に驚いたという逸話が残っております。 |
| 明治44年、鏡如上人(光瑞門主)は、その功を賞して特別賞与第一種と「操心院」の院号を追贈されております。また大正5年には、政府から従五位を贈られています。 |