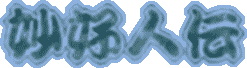
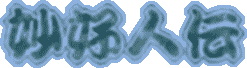
芸州九右エ門男(むすこ)むすこ
| 安芸国加茂郡長浜といふ所に、九右衛門といふ船士(ふなびと)あり。 専修念仏(せんじゅねんぶつ)の行者にて、後に剃髪(ていはつ)して休夢(きゅうむ)といふ。 其子兄弟、船にて伊予国の上島(うわじま)へ往返するを勝計(かっけい)とす。 |
|
元禄三年八月十五日の夜、伊予の五々島の沖にて、難風にあひて船破れんとする時、兄想四郎といへるもの、弟想吉に対していふやう、 「先祖より浄土真宗の御流にて、現世の寿福は祈らざれども、此期におよびては金毘羅大権現をたのみ、この危難をまぬかれんと思ふ。今ここにて二人とも相果(あいはて)なば、親のなげき想像(おもいやる)べし。なんとしてなりとも命をたすかるが、親にも孝行の道理にあらずや」 |
|
と、理害を説て談じければ、弟はあきれはてたる顔色(がんしょく)にて、 「そも何事や。仏祖知識もないがしろにしたる事を申さるるものかな。教(おしえ)を守りて浄土へ往生すれば、親子兄弟も同じ蓮台に乗ずるとこそ聞つれ。教にそむきなば、自業に牽(ひか)れて後生はちりぢりとなりて、親子ふたたび逢うこともならぬが不孝にあらずや。前業の所感、死の縁、無量なれば、陸(くが)にてしぬるも、一生海にて終るも業感。今生は夢の世なり。倒瀾(なみたつ)中にて今命終らば、直に百宝蓮台に昇る身にあらずや。神々へ御苦労かけたてまつらんは、御宗意のきこえぬ先の事でこそあれ」 |
|
と、返答すれば、兄は涙をながし、 「さてもさてもでかしたりでかしたり。我はもとより其心なれども、汝は年わかきゆゑ所存のほどおぼつかなく、今この時におよぶゆゑ、心中を試みたるなり。両人ともに心を合せて祖師、善知識の御跡(みあと)をしたひ奉り、いざ極楽へまゐるべし。去ながら死骸を失ひては、二親の歎きたまはん」 |
|
とて、帆綱をもつてからだを帆柱にくくりつけ、称名念仏の声と共に波にゆられ居けるが、其時五々島の八幡宮、あらたに神主并にその所の庄屋役人へ告させ給ふやうは、 「今この沖に難船あり。いそぎたすけ船を出すべし」 と、神託験(いちじる)し。されど夢の心地にて猶眠さめざりければ、神いかり給ふ御声にて、 「早くすくふべし」 と、再三の御告におどろきて、皆々浜辺に出て互に夢のおもむきを語り合、速(すみやか)に船を出しけるに、波風あらき沖中に涛(なみ)うちこみて、既に沈みかけたる船あり。 |
|
漸(ようや)くなぎさに引よせ来りて見れば、両人の死骸あり。人々打寄り、藁火(わらび)などをたきてあたためければ、兄弟、忽(たちまち)によみがへり、上件のむねをかたれば、人々感じ入り、念仏行者は、たのまざれども神慮(しんりょ)にかなひて、神明(しんみょう)の守り給ふ事を仰がぬものはなかりしとなり。 |
|
扨又(さてまた)故郷の長浜のかたには、其所の明神より神主并に親九右衛門が家に、くはしく御告ありて、 「早く伊予の五々島へたづね行べし」 との神託によりて、早船にてたづねきたり。 |
|
双方の夢物語を合せて、両社の神主をはじめ両所の庄屋・浦人・船子のたぐひ、一同に専修念仏の祖教に帰したてまつりしとなり。 |
|
この由来を委(くわし)くしたため、絵馬のごとくにして、両国の氏神の社檀にかけて諸人にしらしむ。 |
|
時に長浜の神主、夫(それ)より浄土真宗にあつく帰依して、同所の住蓮寺の門徒となり、今に至るまで家内法義を大切によろこばるるとなり。この義(いはれ)によりて、今に至るまで長浜明神の祭礼のみぎり、毎年住連寺の住僧、阿弥陀経を読誦する事を式とするよし、委く承り侍りぬ。 |
|
因に示す。一切の神明の恩徳の重事を略して、五種をあぐ。 一、和光同塵恩 二、随機結縁恩 三、賞罰現前恩 四、願海引入恩 五、信徳護持恩 こころだにまことの道にかなひなば祈らずとても神や守らむ |