

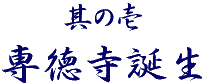
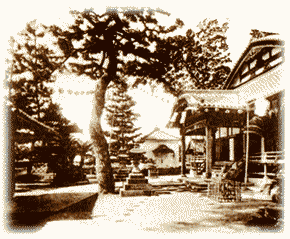
| 専徳寺の誕生は、今からおよそ580年も昔にさかのぼります。 禅宗臨済派の高僧で、愚中禅師という方が、九州教化からの帰りに、平氏小早川春平公に迎えられて安芸の地に留まり、豊田郡許山村、御許山仏通寺(現在の臨済宗仏通寺派本山)を建立して、国内を巡化していました。 そんな折、愚中禅師は、三方を山に囲まれ、南に海を臨むこの長浜の地を見て、大変気に入り、寺院建立をすすめておりました。 そのころ、仏通寺は国の祈願護国寺として、勢力をひろげていた時期でもあり、本郷沼田城主、小早川熈平氏は、戦死者の冥福を祈ると同時に、支配の及ぶ拠点として、この長浜の地に一宇を建立して、嶺宿山専徳院と名づけられました。 時に応永27年(1429)のことであります。 専徳院が最初に建てられたのは、現在観音さんと呼ばれているお堂(観音堂)のある場所で、山の中腹に東西2間3尺、南北3間の同宇が建てられ、普賢菩薩をまつって普賢閣と名づけられていたようであります。 |
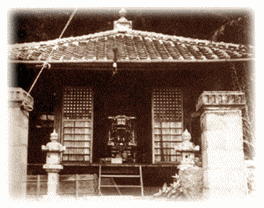 |
観音堂
| 元禄年間の火災によって、当時の詳しい記録は残っていませんが、仏通寺に伝わる古書によると、「専徳院落成後に仏通寺内の永徳院の住持、一笑禅慶大和尚を以って移住させた」と記されています。このことから、一笑禅慶大和尚が禅宗専徳院の開基であると考えられています。 そして、当時仏通寺の中本山として、予州菊間・北条・堀江等、賀茂郡黒瀬郷・広郷等の、凡そ数十寺を管理していたとも記されています。 しかし、当時のお寺は村人とほとんど縁がなく、お堂に本山から派遣された僧侶が、修行しながら仕えているだけの状態ですから、後の一鑑坊に至るまでの約100年の間は、全く判っていません。 |