

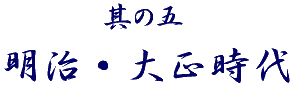
江戸から明治にかけて、石泉和上によって培われた「安芸門徒」のご法義は、大衆の心に深く根を下ろしていきました。
しかし、専徳寺は11世から16世までの住職が、約30年の間に次々と亡くなってゆくという悲劇にみまわれ、その度に住職不在の時が続き、衰退の一途をたどってゆきました。
明治10年、荒廃した専徳寺に入寺してこられたのが、第17世順道であります。順道の入寺によって専徳寺は一変し、その厳しい教えと風習が培われ、この長浜のみならず、広村全体の地に深く浸透していきました。
明治43年には、全国の模範村として表彰され、光瑞門主がその功を祝して、翌44年に専徳寺へ御下向され、盛大に御親修法要がつとまりました。

光瑞御門主をお出迎え
◆『広村』 第3章 宗教 第1節 宗派並施設
(大正4年 警眼社発行) より本村二千六百余戸一万五千の住民は、二戸の神職を除くの外、全部真宗信徒にして、且つ斉しく本派本願寺に属せり。而して其の信仰の旺なること他に多く其比を見ず。随って世道人心に及ぼせる感化、最も偉大なるものあり。・・・・・・・事情既に斯くの如くなるを以って、村民の寺院に対する尊敬の念最も高く、其維持経営に就いては、喜び進んで身心を労し、資材を投ずるに後れんことを恐る。近く数年間に於て、寺院の再建、修繕等に寄附せるもののみにて実に二万円に及べるの事実、亦以って其一般を窺ふに足るべし。寺は真光寺・善通寺・専徳寺・住蓮寺の四箇寺、外に説教所六箇所あり。
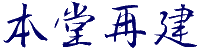
明治21年から再建にかかり、翌年に現在の本堂が完成しております。
専徳寺の本堂は、起(むく)りの屋根をいただき、外陣は7間4面で柱の無い全国でも類を見ない建築様式となっています。これは、話しやすく、また聴聞しやくするために、聞法第一の思いを込めて建てられたためです。
明治37年、義俊が第18世住職を継職しましたが、明治43年に39歳の若さで還浄されました。その時法嗣義淳はわずか9歳。また、順道が陣頭にたって教化されました。
そして、大正11年、義淳が第19世を継職しました。